「手。」
アルルは時折理不尽な要求をする。今も、そうだ。
「手、見せて。」
「何故。」
「いいから。」
溜息をついて言われるままに手を差し出す。
面白くも何ともないだろうに彼女は差し出された手を興味深げに見ている。
筋張った自分の手をとる彼女の手は小さく柔らかい、まさしく年頃の少女の手だった。
「何してる?」
「匂い、どんな匂いがするのかなって。」
ぎゅ、と筋張った手を抱きしめて顔を近づけるのにくすぐったささえ覚えて「離せ」と振りほどいた。
「・・・シェゾの匂いしかしないね。」
「当たり前だ。」
それ以外の匂いがしたらおかしいだろう。
その答えに彼女は首を傾げて、「ん。」手を差し出した。
人間の匂い、彼女が好きだと言っていた甘い匂い、この近辺に咲いている花の匂い、それに混じって
ほのかに鉄臭い匂いが鼻についた。
おおよそ彼女に似つかわしくないはずの香りに違和感を覚えることはない。
それだけ彼女に毒されている自分を自覚しながら、彼女の期待通りに訊いてやることにする。
「魚でも捌いたか。」
「ううん。」
「肉でも切ったんだろ。」
「ううん。」
「怪我の手当でもしたのか。」
「ううん。」
「魔物を殺したか。」
「うん。」
「いつ。」
「三日くらい、前かな。」
「曖昧だな。」
「いつものことだし。」
「どうやって殺したんだ。」
「普通に。魔法で。」
「ならどうしてこんな匂いがするんだ。」
「知らない。なんで?」
「オレに訊くな。」
「それもそうだね。」
アルルはまじまじと自分の掌を眺めて、時々確認するように匂いを嗅いでいる。
その手はさぞや多くの鉄錆の匂いに包まれているんだろう、彼女はある意味平等だ。
あ、声がして「これ、ボクの匂いだ。」鉄の匂いを自分だと認識する。認識して、そして受け入れた。
いつからこんな匂いになったんだっけ?きょと、と首を傾げるアルルにそら恐ろしい思いを抱きながら
「知るか。」とだけシェゾは言った。
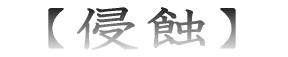
ひたひたと紅に侵される